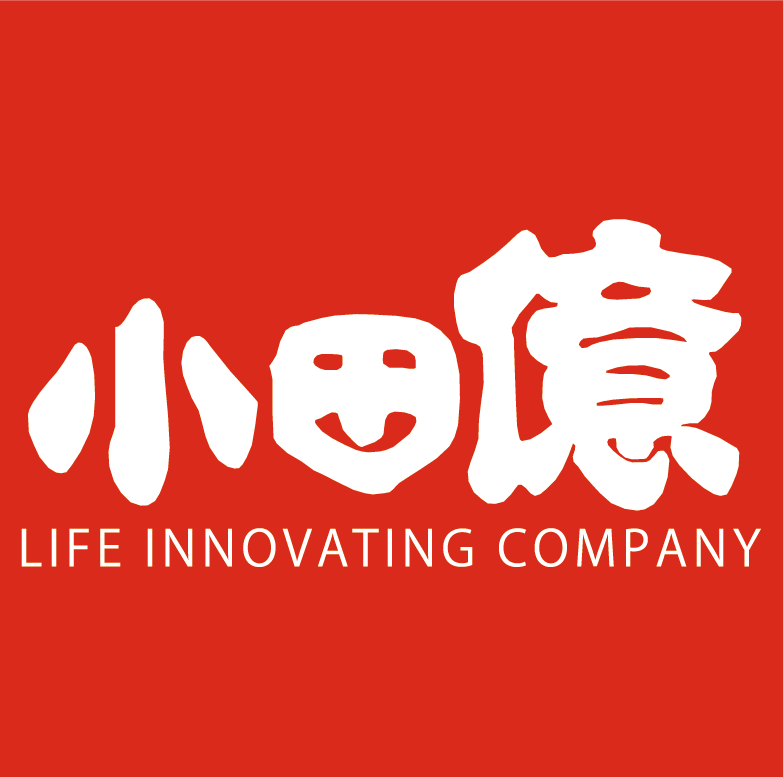翼よわが命
小田億株式会社の家具事業創業者である、(故)小田勇による飛行機乗りや事業家としての生涯を綴った本人による著書です。
どなたでもご自由にダウンロードして、ご覧ください。
小田 勇
大正4年11月23日 広島市安佐南区緑井に生まれる。
昭和11年、山梨飛行学校卒業。
【書籍情報】
- 書籍名
- 翼よわが命
- 著者名
- 小田 勇
- ページ数
- 214ページ
- 企画・編集
- 中国新聞社
- 発行日
- 平成2年11月23日
スマホにてご覧になられる方はコチラから
書籍のPDFデータダウンロード(無料)はコチラから
要約と解説
帰郷
“原子爆弾”に違いない
『結婚式に来てもらうため、両親を迎えに八月六日、広島へ帰ることにした。駅へ出たが広島行きの汽車が不通だという。この日、広島に”新型爆弾”が落とされたことを私はまだ知らなかった。七日も不通。八日の夜、初めて広島通過の汽車が出た。
夜明け前、汽車は福山駅を通過した。「わあ、こりゃどうなろうに」? 福山の街がボンボン燃えている。八月九日の夜が明けた。中野駅を過ぎたころから「あれ、おかしいぞ」と思った。向洋にくると家の倒れ方が全部同一方向、一方的に爆風を受けて壊れている。「どうしたんかのう」。汽車は広島駅に止まった。「アッリャー」
しばらく呆然とたたずんだ。家が一軒もない。宇品が見える。駅前をうろつく。遺体があっちこっちに転がったまま。川にも浮いている。凄惨の一語に尽きた。 汽車は広島駅に三十分ぐらい止まっていた。駅員が「広島通過はこの汽車が初めてです」と話していた。その汽車で横川駅へ降り立った。 ここもー望千里、わが家は横川駅から南三百㍍の太田川沿いにあるはずだった。そのわが家もない、倉庫も見えない。川にはまだ遺体が浮いていた。陸には人の遺体は少なかったが 犬や馬の死体が方々にあった。ともかくひどいもんだった。無性に腹がたった。
十日ほど前、滋賀県八日市の部隊に父から手紙をもらっていた。「かねて疎開用にと建て かけていた佐伯郡湯来町の家が、なんとか入れるようになったので、家族全員が取りあえず 疎開したから安心するよう」との文面だった。家や倉庫は全滅したが家族は疎開しているか ら大丈夫、そう思っていた。
廃虚と化したわが家の焼け跡に、いつまでただずんでいてもどうしようもない。広島県佐 伯郡五日市町(現在広島市佐伯区)にうちの山の現場を引き受けてくれていた清水和一さんという人がいた。そこへ立ち寄った。立ち寄ったといっても横川から五日市まで、どうやっ て行ったか不思議に記憶がないんだ。どうやってといっても、乗り物がないんだから多分歩 いて行った、としか考えられないのに覚えがない。 清水さんは「パラシュートの付いた爆弾がニ個落ちた。五日市からよく見えた」と言った。 たったのニ個で広島が吹っとんだ ? とっさに私はこりゃ原子爆弾だ、と直感した。
八日市飛行場の部隊にいる時、東京大学航空科の守屋富次郎教授の講義を受けていた。再々の面識が あったからよく話した。
彼のロから「原子爆弾」というものが研究されていることを初めて聞いた。私は「その原子爆弾はこの戦争に間にあうか」と聞いた。「いや、この戦争には間にあわん。いずれは出来るだろうが、出来たら大ごとになる」。
そんな話を、それもつい最近聞いたばかりだったからだ。
「亡くなられた小田億の…」
ともあれ、家族の疎開先、湯来町へ急いで帰らねばならん。清水さん宅を辞して道路で廿 日市方面行きのトラックを待っていた。
いつ通るかわからないトラックに便乗させてもらう しか「足」はない。同じ場所でもう一人、五、六十歳の男の人が同じようにトラックを待っていた。「小田億の息子ですが、トラックの来るのを待ってます」「ああ、亡くなられた小田億の息子さんですか」「そうです」。
ピンとこなかった。「小田億の息子」に対して「そうです」 と答えたが…ええ?何と言ったこの人は。たしか「亡くなられた」と言ったようだが。 「あのう、親父は死んだんですか」「ええ、そう聞きましたが…」「死体は確認されたようですか」「あったらしい」
こりゃ大変だ。父たちはてっきり湯来へ疎開しているとばかり信じていたのに。
通りがかったトラックに便乗させてもらい、はやる心を抑えながら湯来町へ。
疎開先には、母と妹と叔母の三人がいた。 父の姿はない。「お父さん、だめじゃったらしいな」「……」だれも返事がない。母が泣きだした。
やっぱりそぅだったのか…親父へのいとおしさ、重なる親不孝への悔恨が頭の中で渦を巻く。
「骨は?」「…あった」? 父は横川の自宅で焼死していた。湯来の疎開先の家屋はまだ完全には出来上がっていなかった。
父はその材料を買ぅため、前日一人で横川に出て、その夜は横川に泊まった。
六日朝早く自転車でどこかへ行き、帰宅したところで原爆に遭ったらしい。崩れた家の梁(はり)に腰を挾まれ、それを両手で突っ張った姿で家と共に焼け死んでいた。父は数えの五十五歳だった。』
“原子爆弾”に違いない
『結婚式に来てもらうため、両親を迎えに八月六日、広島へ帰ることにした。駅へ出たが広島行きの汽車が不通だという。この日、広島に”新型爆弾”が落とされたことを私はまだ知らなかった。七日も不通。八日の夜、初めて広島通過の汽車が出た。
夜明け前、汽車は福山駅を通過した。「わあ、こりゃどうなろうに」? 福山の街がボンボン燃えている。八月九日の夜が明けた。中野駅を過ぎたころから「あれ、おかしいぞ」と思った。向洋にくると家の倒れ方が全部同一方向、一方的に爆風を受けて壊れている。「どうしたんかのう」。汽車は広島駅に止まった。「アッリャー」
しばらく呆然とたたずんだ。家が一軒もない。宇品が見える。駅前をうろつく。遺体があっちこっちに転がったまま。川にも浮いている。凄惨の一語に尽きた。 汽車は広島駅に三十分ぐらい止まっていた。駅員が「広島通過はこの汽車が初めてです」と話していた。その汽車で横川駅へ降り立った。 ここもー望千里、わが家は横川駅から南三百㍍の太田川沿いにあるはずだった。そのわが家もない、倉庫も見えない。川にはまだ遺体が浮いていた。陸には人の遺体は少なかったが 犬や馬の死体が方々にあった。ともかくひどいもんだった。無性に腹がたった。
十日ほど前、滋賀県八日市の部隊に父から手紙をもらっていた。「かねて疎開用にと建て かけていた佐伯郡湯来町の家が、なんとか入れるようになったので、家族全員が取りあえず 疎開したから安心するよう」との文面だった。家や倉庫は全滅したが家族は疎開しているか ら大丈夫、そう思っていた。
廃虚と化したわが家の焼け跡に、いつまでただずんでいてもどうしようもない。広島県佐 伯郡五日市町(現在広島市佐伯区)にうちの山の現場を引き受けてくれていた清水和一さんという人がいた。そこへ立ち寄った。立ち寄ったといっても横川から五日市まで、どうやっ て行ったか不思議に記憶がないんだ。どうやってといっても、乗り物がないんだから多分歩 いて行った、としか考えられないのに覚えがない。 清水さんは「パラシュートの付いた爆弾がニ個落ちた。五日市からよく見えた」と言った。 たったのニ個で広島が吹っとんだ ? とっさに私はこりゃ原子爆弾だ、と直感した。
八日市飛行場の部隊にいる時、東京大学航空科の守屋富次郎教授の講義を受けていた。再々の面識が あったからよく話した。
彼のロから「原子爆弾」というものが研究されていることを初めて聞いた。私は「その原子爆弾はこの戦争に間にあうか」と聞いた。「いや、この戦争には間にあわん。いずれは出来るだろうが、出来たら大ごとになる」。
そんな話を、それもつい最近聞いたばかりだったからだ。
「亡くなられた小田億の…」
ともあれ、家族の疎開先、湯来町へ急いで帰らねばならん。清水さん宅を辞して道路で廿 日市方面行きのトラックを待っていた。
いつ通るかわからないトラックに便乗させてもらう しか「足」はない。同じ場所でもう一人、五、六十歳の男の人が同じようにトラックを待っていた。「小田億の息子ですが、トラックの来るのを待ってます」「ああ、亡くなられた小田億の息子さんですか」「そうです」。
ピンとこなかった。「小田億の息子」に対して「そうです」 と答えたが…ええ?何と言ったこの人は。たしか「亡くなられた」と言ったようだが。 「あのう、親父は死んだんですか」「ええ、そう聞きましたが…」「死体は確認されたようですか」「あったらしい」
こりゃ大変だ。父たちはてっきり湯来へ疎開しているとばかり信じていたのに。
通りがかったトラックに便乗させてもらい、はやる心を抑えながら湯来町へ。
疎開先には、母と妹と叔母の三人がいた。 父の姿はない。「お父さん、だめじゃったらしいな」「……」だれも返事がない。母が泣きだした。
やっぱりそぅだったのか…親父へのいとおしさ、重なる親不孝への悔恨が頭の中で渦を巻く。
「骨は?」「…あった」? 父は横川の自宅で焼死していた。湯来の疎開先の家屋はまだ完全には出来上がっていなかった。
父はその材料を買ぅため、前日一人で横川に出て、その夜は横川に泊まった。
六日朝早く自転車でどこかへ行き、帰宅したところで原爆に遭ったらしい。崩れた家の梁(はり)に腰を挾まれ、それを両手で突っ張った姿で家と共に焼け死んでいた。父は数えの五十五歳だった。』
以上は私の父である小田勇が広島を家で同然で飛び出し、空の世界へ羽ばたき、結婚が決まった報告に帰郷した時の記憶を後に記したものです。
私の父、小田勇がなくなって11年経つ今でも多くの方々から小田億と飛行機やグライダーに関する質問をお受けすることが多く、小田億と飛行機、そして原爆、戦前からの木材業の復興、そして家具販売業に至るヒストリーを少しでも多くの方にお伝えしておくべきではないかと考え、筆をとりました。
小田億の創業者は小田億人(読みはおくと、原爆にて没)で、湯来町に生まれました。
その長男である小田勇は幼い頃から飛行機に憧れ、その想いを実現すべく、飛行機乗りの世界へ飛び込みました。
家出同然で山梨の飛行学校に入学し、その熱心さと持ち前の飛行技術の才能により、飛行学校を主席で卒業した小田勇はその後、飛行機やグライダーの世界で大きくその才能を花開かせることになったのです。
テストパイロット、教育に従事する傍ら、各種競技にも出場し、日本でトップパイロットの座を固めていったのです。
その後の原爆投下、終戦を経て、小田勇は広島に帰郷すると同時に父への弔いとして家業を復興することを決意します。その後、グライダー世界選手権日本代表として多くの国に日本代表として派遣されます。
その経験を通じて冒頭の「帰郷」、そして「小田億家具」創業を決意するまでの経緯を小田勇本人の平成2年に書き記した著書、「翼よわが命」から抜粋してご紹介していこうと思います。
私の父、小田勇がなくなって11年経つ今でも多くの方々から小田億と飛行機やグライダーに関する質問をお受けすることが多く、小田億と飛行機、そして原爆、戦前からの木材業の復興、そして家具販売業に至るヒストリーを少しでも多くの方にお伝えしておくべきではないかと考え、筆をとりました。
小田億の創業者は小田億人(読みはおくと、原爆にて没)で、湯来町に生まれました。
その長男である小田勇は幼い頃から飛行機に憧れ、その想いを実現すべく、飛行機乗りの世界へ飛び込みました。
家出同然で山梨の飛行学校に入学し、その熱心さと持ち前の飛行技術の才能により、飛行学校を主席で卒業した小田勇はその後、飛行機やグライダーの世界で大きくその才能を花開かせることになったのです。
テストパイロット、教育に従事する傍ら、各種競技にも出場し、日本でトップパイロットの座を固めていったのです。
その後の原爆投下、終戦を経て、小田勇は広島に帰郷すると同時に父への弔いとして家業を復興することを決意します。その後、グライダー世界選手権日本代表として多くの国に日本代表として派遣されます。
その経験を通じて冒頭の「帰郷」、そして「小田億家具」創業を決意するまでの経緯を小田勇本人の平成2年に書き記した著書、「翼よわが命」から抜粋してご紹介していこうと思います。
空へのあこがれ
「アッあれが飛行機だ」
その時、私は驚いて空を見あげた。何ごとが起こったか、生まれて初めて聞く激しい音で ある。銀色に輝く物体が、材木の上で一人遊びしていた私の方にぐんぐん近づいてくる。
「アッ、飛行機だ!あれが飛行機だ」。
まばたきもせず、初めて見る機影を追った。高度は百mぐらいか。複葉だった。私の頭上を通る。すごい爆音だ。ぞくぞくする感動が頭の 中を走り抜けた。緑井小学校一年の時だった。春か、夏か、それは記憶にない。
当時、父小田億人(原爆で五十五歳で死亡)は太田川支流沿いの緑井で材木店をやっていた。 家の裏から川にかけ広い材木置場があった。この広場が幼時の私の遊び場だった。材木の上 によじ登つたり、飛び降りたりして…。
「アッあれが飛行機だ」
その時、私は驚いて空を見あげた。何ごとが起こったか、生まれて初めて聞く激しい音で ある。銀色に輝く物体が、材木の上で一人遊びしていた私の方にぐんぐん近づいてくる。
「アッ、飛行機だ!あれが飛行機だ」。
まばたきもせず、初めて見る機影を追った。高度は百mぐらいか。複葉だった。私の頭上を通る。すごい爆音だ。ぞくぞくする感動が頭の 中を走り抜けた。緑井小学校一年の時だった。春か、夏か、それは記憶にない。
当時、父小田億人(原爆で五十五歳で死亡)は太田川支流沿いの緑井で材木店をやっていた。 家の裏から川にかけ広い材木置場があった。この広場が幼時の私の遊び場だった。材木の上 によじ登つたり、飛び降りたりして…。

広島市三篠小学校時代、自宅裏の太田川は貯木と運搬船でにぎわっていた。(自宅は左から3軒目の2階逮て)
幼少時代
超低空で通り過ぎた飛行機は川沿いに北上 したかと思うと、大きく旋回しながらまた私の頭上を飛んだ。「ワーッすごい」再び旋回して南の空に小さくなっていく。まんじりともせず、青空に消えてゆく機影を見つめた。
「よしっ、大きゅうなったら、僕は絶対、飛 行機乗りになるぞ!。」
南の空に残像を求めてたたずんだ。
何かしら、強烈な興奮に小さな胸はかきたてられた。五分か、いや三分だったかもしれない。何の予告もなしに突然、降ってわいたこの出来ごとが、私の人生を決定づけようとは父も母も予想だにしなかっただろう。親不孝の始まりである。
今でもあの時の異常なまでの感動が不思議でならない。宿命というのか、運命というのか、私は適当な言葉を知らない。が、あの銀色に輝く複葉機との瞬間的なめぐりあいで、私の人生が決定づけられたことに人為の及ばぬそら恐ろしさを感じることがある。幼、少年期、人はみな現実ばなれの夢をもつ。特急の機関士に、プロ野球選手にと。その意味では私も、たまたまやっかいな飛行機に、それも執念深く取り付かれたとでも言うべきか。
私の耳の底には六十数年前のあの爆音が、いまだに 残っている。
少年時代
ああ「翼よあれがパリの灯だ」
飛行機乗りになっちゃろー。その気はずっとあった。あっても飛行機乗りになる方法がわ からない。中学低学年のころは飛行機関係の本や雑誌もなかった。
広島東練兵場に、時々陸 海軍の飛行機がやってきた。学校をさぼってまで見に行った。もちろん先生には怒られた。
父に「どうしても飛行機乗りになりたい」と相談した。が、まだ本気には取り合ってくれな い。
中学高学年(13歳から14歳)になったころ、航空記者渡辺一英氏編集の「グライダー」や「航空時代」とい う雑誌が出だした。むさぼるように読んだ。
「模型飛行機からグライダーへグライダーか ら飛行機へ」のねらいで雑誌には優秀模型飛行機の設計図が付録に付いていた。大西洋横断 飛行をやり遂げた空の王者リンドバーグの「翼よあれがパリの灯だ」という本が出た。胸 おどり血騒ぐ、そんな思いで読みふけった。学校の勉強どころではない。
雑誌「航空時代」の付録に付いた設計図をたよりに、家の倉庫で半年かけて地上練習機を 作り上げた。原寸の半分の大きさ。操縦桿(かん)を動かせば昇降舵(だ)も動く。
左右の足を踏めば方向舵(だ)も動く。機体が重いから、もちろん空に浮くようなシロモノ ではない。しかし、風さえあれば本物の飛行機やグラィダーの感触だけはつかめた。待望の大風の日がきた。あれはたしか室戸台風じゃなかったかと思ぅんだ。會庫か ら引っ張り出した。操縦桿、方向舵がいい感じで動く。一生懸命練習していたら突風が吹いた。機体ごと吹き飛ばされてひっくり返った。シートベルトなど作ってはいないから、もののみごと私は地上に投げ出された。不思議とけがもしなかった。半年かけた機体は修理不能に壊れたが飛行機熱は日々にエスヵレートしていくばかり。
そんな調子だから「学業成績極めて優秀」なはずがない。学友たちは高校、専門学校へと 進んでいくが、私の進む道はただ一つ。「飛行学校」の四文字しかなかった。
両親の反対を押し切って私は飛行機乗りになった。一生涯「親不孝」の重荷を背負い込ん で生きてきた。家業は継がない、危ないグラィダーにうつつを抜かす、山の木は監督不行き 届きで大損させる。飛べば落ち、飛べば落ちる時代の飛行士の道をあえて求めてゆく?おや じには本当に心配ばかりさせてきた。そのおやじは終戦も知らず原爆で死んだ。勇はまだ飛 行機に乗ってる?と心配しているだろうな。戦後、焦土の中で「おやじ、すまぬ、すまぬ」 と私が必死になって材木店を再興した姿を、おやじは知らない。
戦後間なしに、先輩であり親友である松下弁ニさんがしんみりした口調で言った。「小田や、 あんたのおやじさん、ほんとに立派だったなあ」。突然、何を言い出すのかと思った。「実は …」
私も驚いた。広島東練兵場時代、福岡へ飛行機に乗せてもらったり、松下さんと親しく付 き合っていることは父も知ってはいただろう。しかし、父と松下さんは一面識もない、はず だった。それがあったのである。私が山梨飛行学校に入ることを決意したころ?父はもちろ ん私には反対の一徹だった。ひそかに父は大阪毎日新聞社へ松下さんを訪ねてきた、というのだ。寝耳に水だった。
「どうしても飛行機乗りになるというが、どうだろうか」「危なくないだろうか」親なれ ばこその素朴な質問だった。「飛行機の性能も昔とは格段に違ってきているし…私らもこう してやってるぐらいですから…小田君はすばらしい天性の素質を持っていることだし…やら されてはどうですか」。松下さんは私のために〃悪者”になってくれた。この対面で父は決 心したょうだ。最後に「本当に飛行機乗りに徹するのなら?それでいいんです。中途半端な 人間にだけはしたくないんです」そう言って帰ったという。
生死を共にやってきた親友の松下さん、十年間もそれを黙っていた。父は最期までついに 言わなかった。松下さんは松下さんらしいと思う。おやじはおやじらしいと思う。ありがた い。
松下さんに、そう打ち明けられてみれば思い当たるふしもある。山梨飛行学校に行くため 家出同様の無一文で飛び出した時、しばらくして父が金を送ってきてくれた。添えた手紙は 何と書いてあったか、ただジーンときたのを思いだす。
超低空で通り過ぎた飛行機は川沿いに北上 したかと思うと、大きく旋回しながらまた私の頭上を飛んだ。「ワーッすごい」再び旋回して南の空に小さくなっていく。まんじりともせず、青空に消えてゆく機影を見つめた。
「よしっ、大きゅうなったら、僕は絶対、飛 行機乗りになるぞ!。」
南の空に残像を求めてたたずんだ。
何かしら、強烈な興奮に小さな胸はかきたてられた。五分か、いや三分だったかもしれない。何の予告もなしに突然、降ってわいたこの出来ごとが、私の人生を決定づけようとは父も母も予想だにしなかっただろう。親不孝の始まりである。
今でもあの時の異常なまでの感動が不思議でならない。宿命というのか、運命というのか、私は適当な言葉を知らない。が、あの銀色に輝く複葉機との瞬間的なめぐりあいで、私の人生が決定づけられたことに人為の及ばぬそら恐ろしさを感じることがある。幼、少年期、人はみな現実ばなれの夢をもつ。特急の機関士に、プロ野球選手にと。その意味では私も、たまたまやっかいな飛行機に、それも執念深く取り付かれたとでも言うべきか。
私の耳の底には六十数年前のあの爆音が、いまだに 残っている。
少年時代
ああ「翼よあれがパリの灯だ」
飛行機乗りになっちゃろー。その気はずっとあった。あっても飛行機乗りになる方法がわ からない。中学低学年のころは飛行機関係の本や雑誌もなかった。
広島東練兵場に、時々陸 海軍の飛行機がやってきた。学校をさぼってまで見に行った。もちろん先生には怒られた。
父に「どうしても飛行機乗りになりたい」と相談した。が、まだ本気には取り合ってくれな い。
中学高学年(13歳から14歳)になったころ、航空記者渡辺一英氏編集の「グライダー」や「航空時代」とい う雑誌が出だした。むさぼるように読んだ。
「模型飛行機からグライダーへグライダーか ら飛行機へ」のねらいで雑誌には優秀模型飛行機の設計図が付録に付いていた。大西洋横断 飛行をやり遂げた空の王者リンドバーグの「翼よあれがパリの灯だ」という本が出た。胸 おどり血騒ぐ、そんな思いで読みふけった。学校の勉強どころではない。
雑誌「航空時代」の付録に付いた設計図をたよりに、家の倉庫で半年かけて地上練習機を 作り上げた。原寸の半分の大きさ。操縦桿(かん)を動かせば昇降舵(だ)も動く。
左右の足を踏めば方向舵(だ)も動く。機体が重いから、もちろん空に浮くようなシロモノ ではない。しかし、風さえあれば本物の飛行機やグラィダーの感触だけはつかめた。待望の大風の日がきた。あれはたしか室戸台風じゃなかったかと思ぅんだ。會庫か ら引っ張り出した。操縦桿、方向舵がいい感じで動く。一生懸命練習していたら突風が吹いた。機体ごと吹き飛ばされてひっくり返った。シートベルトなど作ってはいないから、もののみごと私は地上に投げ出された。不思議とけがもしなかった。半年かけた機体は修理不能に壊れたが飛行機熱は日々にエスヵレートしていくばかり。
そんな調子だから「学業成績極めて優秀」なはずがない。学友たちは高校、専門学校へと 進んでいくが、私の進む道はただ一つ。「飛行学校」の四文字しかなかった。
両親の反対を押し切って私は飛行機乗りになった。一生涯「親不孝」の重荷を背負い込ん で生きてきた。家業は継がない、危ないグラィダーにうつつを抜かす、山の木は監督不行き 届きで大損させる。飛べば落ち、飛べば落ちる時代の飛行士の道をあえて求めてゆく?おや じには本当に心配ばかりさせてきた。そのおやじは終戦も知らず原爆で死んだ。勇はまだ飛 行機に乗ってる?と心配しているだろうな。戦後、焦土の中で「おやじ、すまぬ、すまぬ」 と私が必死になって材木店を再興した姿を、おやじは知らない。
戦後間なしに、先輩であり親友である松下弁ニさんがしんみりした口調で言った。「小田や、 あんたのおやじさん、ほんとに立派だったなあ」。突然、何を言い出すのかと思った。「実は …」
私も驚いた。広島東練兵場時代、福岡へ飛行機に乗せてもらったり、松下さんと親しく付 き合っていることは父も知ってはいただろう。しかし、父と松下さんは一面識もない、はず だった。それがあったのである。私が山梨飛行学校に入ることを決意したころ?父はもちろ ん私には反対の一徹だった。ひそかに父は大阪毎日新聞社へ松下さんを訪ねてきた、というのだ。寝耳に水だった。
「どうしても飛行機乗りになるというが、どうだろうか」「危なくないだろうか」親なれ ばこその素朴な質問だった。「飛行機の性能も昔とは格段に違ってきているし…私らもこう してやってるぐらいですから…小田君はすばらしい天性の素質を持っていることだし…やら されてはどうですか」。松下さんは私のために〃悪者”になってくれた。この対面で父は決 心したょうだ。最後に「本当に飛行機乗りに徹するのなら?それでいいんです。中途半端な 人間にだけはしたくないんです」そう言って帰ったという。
生死を共にやってきた親友の松下さん、十年間もそれを黙っていた。父は最期までついに 言わなかった。松下さんは松下さんらしいと思う。おやじはおやじらしいと思う。ありがた い。
松下さんに、そう打ち明けられてみれば思い当たるふしもある。山梨飛行学校に行くため 家出同様の無一文で飛び出した時、しばらくして父が金を送ってきてくれた。添えた手紙は 何と書いてあったか、ただジーンときたのを思いだす。
その後のパイロットとしての活躍はあまりにも長くなるため本文ダウンロードにてご確認いただけれと思います。
戦後、航空禁止令が解除された後、小田勇は日本のグライダーパイロットの代表として「世界グライダー選手権大会」参加、世界中の空を飛び回ることになった。
第1回目はポーランド、2回はフランス。3回目出場は昭和35年西ドイツのケルンで行われた「第8回世界グライダー選手権大会」である。
小田勇はこのときの想い出を後に以下の通り語っている。
戦後、航空禁止令が解除された後、小田勇は日本のグライダーパイロットの代表として「世界グライダー選手権大会」参加、世界中の空を飛び回ることになった。
第1回目はポーランド、2回はフランス。3回目出場は昭和35年西ドイツのケルンで行われた「第8回世界グライダー選手権大会」である。
小田勇はこのときの想い出を後に以下の通り語っている。
「この時の自由飛行ではケルンをスタートして、ともかく北へ北へと飛んだ。四百㌔ぐらい飛んだだろうか。大きな川にさしかかった。エルベ川である。茶色く濁った川の対岸が見えないほど広い。維持している高度では対岸まで飛びきれそうにない。引き返して川辺の畑へ降りた。着陸したら大勢の人が寄ってきた。警察官も来た。身ぶり手ぶりで話してみたら、この警察官はかつて外国航路の船に乗っており、日本へも度々寄港し東京、横浜、神戸のことをよく知っていた。実に好意的だった。
そんなところへ老夫婦がフォルクスワーゲンで乗り付けてきた。笑顔でいきなり「うちへ飯を食いに来い」という。警察官は「行ってこい。グライダーは曳航車が来るまで私が責任を持って守ってやる」という。招かれるままに老夫婦宅へ行ったら、農家らしいが広い庭のある豪邸だった。
庭に大きな農耕機械が置いてあった。「風呂へ入れ」「のもうや」でビールをご馳走してくれた。 挙句の果ては親父さんすっかり酔っ払ってしまった。酔っ払っても身振り手振りで「日本はよう頑張った」「ドイツが手をあげても頑張った」とか「日本もドイツもようやったんだがイタリアがつまらんかった」親父さんの放言をほどほどに聞き流しながら私の心はこの豪邸の家具にすっかり魅了されていた。実に立派だった。何がどう立派だったかは一口では言えないが、成金的なきらびやかさではなく調度品が豪邸にしっくりと落ち着いている。特に食堂に置かれた家具に調和のとれた貫禄を感じた。その夜はこの家に泊めてもらった。 ハンブルグの郊外だったかと思う。」
そんなところへ老夫婦がフォルクスワーゲンで乗り付けてきた。笑顔でいきなり「うちへ飯を食いに来い」という。警察官は「行ってこい。グライダーは曳航車が来るまで私が責任を持って守ってやる」という。招かれるままに老夫婦宅へ行ったら、農家らしいが広い庭のある豪邸だった。
庭に大きな農耕機械が置いてあった。「風呂へ入れ」「のもうや」でビールをご馳走してくれた。 挙句の果ては親父さんすっかり酔っ払ってしまった。酔っ払っても身振り手振りで「日本はよう頑張った」「ドイツが手をあげても頑張った」とか「日本もドイツもようやったんだがイタリアがつまらんかった」親父さんの放言をほどほどに聞き流しながら私の心はこの豪邸の家具にすっかり魅了されていた。実に立派だった。何がどう立派だったかは一口では言えないが、成金的なきらびやかさではなく調度品が豪邸にしっくりと落ち着いている。特に食堂に置かれた家具に調和のとれた貫禄を感じた。その夜はこの家に泊めてもらった。 ハンブルグの郊外だったかと思う。」
このころの日本はまだ戦後の復興の最中であり、特に故郷の広島は原爆の廃墟から立ち直る途上にあった。
小田勇は強くヨーロッパの家具そして暮らしに衝撃を受けた。
次に家具に対する衝撃を受けたのは昭和38年2月「第9回グライダー世界選手権アルゼンチン大会」での出来事だった。
その時の様子を小田勇は以下のように語っている。
小田勇は強くヨーロッパの家具そして暮らしに衝撃を受けた。
次に家具に対する衝撃を受けたのは昭和38年2月「第9回グライダー世界選手権アルゼンチン大会」での出来事だった。
その時の様子を小田勇は以下のように語っている。
『何回目だったか、アルゼンチン大会も終わりに近いころだった。うそのようなピンチに見舞われた。
二百五十㌔ぐらい飛んで、帰りを飛行機曳航で引っ張ってもらっていたらなんとまあ、飛行機のパイロットが帰る道を迷うてしまったのだ。アルゼンチンという国はたしかに広い。そして空を飛ぶのに地上に目標物が少ない。とはいいながら、飛行機乗りが自分の国で迷子になってしまうとは恐れ入った。
ともかく帰る飛行場がわからんままに空の上で日が暮れた。飛行機もそうだがグライダーの夜間着陸というのは非常に危ない。日はとっぷり暮れて周囲がほとんど見えなくなってしまった。飛行機は強行着陸するという。私も覚悟を決めた。飛行機はグライダーより先に着陸する。飛行機には翼灯が付いている。飛行機の翼灯が無事降りたらすぐ近くに着陸しよう。翼灯がひっくり返ればそこへは降りまいと。飛行機が曳航索を放せ、と翼を振る。離脱した。飛行機の翼灯はうまいこと着陸した。よし、あそこへ・・・、と十㍍ぐらい離れた地点に降りた。やれやれ、と機外へ出て見たら、グライダーの鼻先十五㍍に牧場の柵が塀のように連なっていた。もうちょっと飛び過ぎていたら盲腸どころの騒ぎじゃない。大けがをするところだった。
空からの夜中の珍客に牧場主がやってきた。「まあ、うちへ来なさい」と言う。大牧場主らしい。大きな家だった。これまた非常に親日的な人だった。「これ、日本の本じゃ 」と差し出された本の表紙には「SABISISA」と書いてあった。佗しさも寂しさもいいんだが、私たちはまだ飯を食っていない。腹ペコの二人に大きなビフテキを焼いてくれた。うまかったなあ。そして、またまたであるが、この牧場主の家の家具に目を輝かせた。立派なのである。殊にベッドが素晴らしかった。日本では、病院はともかく一般家庭の中にベッドはまだ普及されていなかった。「帰国したら、こりゃどうしても家具をやろう」と決心した。』
二百五十㌔ぐらい飛んで、帰りを飛行機曳航で引っ張ってもらっていたらなんとまあ、飛行機のパイロットが帰る道を迷うてしまったのだ。アルゼンチンという国はたしかに広い。そして空を飛ぶのに地上に目標物が少ない。とはいいながら、飛行機乗りが自分の国で迷子になってしまうとは恐れ入った。
ともかく帰る飛行場がわからんままに空の上で日が暮れた。飛行機もそうだがグライダーの夜間着陸というのは非常に危ない。日はとっぷり暮れて周囲がほとんど見えなくなってしまった。飛行機は強行着陸するという。私も覚悟を決めた。飛行機はグライダーより先に着陸する。飛行機には翼灯が付いている。飛行機の翼灯が無事降りたらすぐ近くに着陸しよう。翼灯がひっくり返ればそこへは降りまいと。飛行機が曳航索を放せ、と翼を振る。離脱した。飛行機の翼灯はうまいこと着陸した。よし、あそこへ・・・、と十㍍ぐらい離れた地点に降りた。やれやれ、と機外へ出て見たら、グライダーの鼻先十五㍍に牧場の柵が塀のように連なっていた。もうちょっと飛び過ぎていたら盲腸どころの騒ぎじゃない。大けがをするところだった。
空からの夜中の珍客に牧場主がやってきた。「まあ、うちへ来なさい」と言う。大牧場主らしい。大きな家だった。これまた非常に親日的な人だった。「これ、日本の本じゃ 」と差し出された本の表紙には「SABISISA」と書いてあった。佗しさも寂しさもいいんだが、私たちはまだ飯を食っていない。腹ペコの二人に大きなビフテキを焼いてくれた。うまかったなあ。そして、またまたであるが、この牧場主の家の家具に目を輝かせた。立派なのである。殊にベッドが素晴らしかった。日本では、病院はともかく一般家庭の中にベッドはまだ普及されていなかった。「帰国したら、こりゃどうしても家具をやろう」と決心した。』
当時の広島は復興は進みつつあったが、原爆の壊滅的な惨禍からは少しづつ立ち直り始めていたものの、人々に残された心身両面での復興はまだまだ道半ばであった。
文中、時期は前後するが小田勇は「翼よ我がいのち」の中で被爆直後の広島を以下のように語っている。
これまでの人生で最大の親孝行だったはずの「結婚報告」が一転、ふるさとの壊滅、そして父親の死。
人知を超えた辛い惨状を目にした。家出同然で実家を飛び出し飛行機乗りに・・・親孝行ができなかった・・・
広島市民がわが街の復興のために市民を盛り上げようと、カンパをしてまで立ち上げた市民球団、広島カープが復興途中の市民の気持ちを鼓舞したように。
今回、グライダー世界選手権大会にてのヨーロッパの古い民家で経験した、決して華美ではなく古いけれども重厚で何代にも渡って使い続けられた本物の家具や豊かな暮らは小田勇の心を強く揺さぶった。「よし、この家具や暮らしを広島に持って帰るぞ!」を復興道半ばの広島市民に届けたいと小田勇は決意した。
文中、時期は前後するが小田勇は「翼よ我がいのち」の中で被爆直後の広島を以下のように語っている。
これまでの人生で最大の親孝行だったはずの「結婚報告」が一転、ふるさとの壊滅、そして父親の死。
人知を超えた辛い惨状を目にした。家出同然で実家を飛び出し飛行機乗りに・・・親孝行ができなかった・・・
広島市民がわが街の復興のために市民を盛り上げようと、カンパをしてまで立ち上げた市民球団、広島カープが復興途中の市民の気持ちを鼓舞したように。
今回、グライダー世界選手権大会にてのヨーロッパの古い民家で経験した、決して華美ではなく古いけれども重厚で何代にも渡って使い続けられた本物の家具や豊かな暮らは小田勇の心を強く揺さぶった。「よし、この家具や暮らしを広島に持って帰るぞ!」を復興道半ばの広島市民に届けたいと小田勇は決意した。

小田億材木店
家具センター小田億の誕生

「小田億家具」華やかに開店
長い長いアルゼンチン世界選手権大会道草の旅だった。一月の末に日本を旅立って、やっ と帰国したのは桜も散った四月の中ごろか。
すぐ家具業の準備にかかる。まず、国内の家具店を回ってみた。大きい所で店舗面積がニ、三百坪ぐらい。よし、そんなら倍の五百三十坪を造ってやろう。やるとなつたらどうせやるんだから家族に心配かけまい、自分も迷うまいとだれにも話さずに猪突猛進。
設計にかかる。その年の九月一日、広島市西区横 川町一丁目の現在地に四階建てのビルが建ちだした。ここまでくれば家族も気付く。「ビル建ててどうするの?」と家内が聞く。「家具をやるんじゃ」。いつものことだから、家内も別に驚くふうもない、もちろん褒めてはくれんが「材木」より「家具」の方が気には入ってい る、そんな感触を受けた。
こんな調子でビル建設は進んだ。規模としては当時、中四国地方では一番大きかった。
翌年、つまり昭和三十九年の春、待望の新事業「家具センター小田億」は華やかに開店し た。オープニングが三月七日、「ラツキーセブン!」と気をよくした。神武か岩戸か知らな いが世の中も隨分華やぎ景気づいた年だった。そうそう、東京オリンピックの年だった。家

具センターが開店して間もなく、これまた念願の自家用飛行機が到着した。さあ、忙しくなった。新事業は発足したばかり、飛行機は乗りたいし、体は一つ。そこで一計、いや、”ひらめき” とでも言わせてもらおう。
「新事業の宣伝、つ まり広告代わりに飛ぼう」。なかなかのグッド アイディアである。
翼へは赤地に白く「小田億家具」、白い胴体には黒字で「小田億家具」。文字を目いっぱい 大きく書き入れた。
たまたま、オリンピックの聖火が広島の街を 走った。沿道は大変な人出でにぎわっていた。 私は空から聖火ランナーに寄り添うような低空 で、飛んでは引き返し、引き返しては飛んだ。 反響は予想をはるかに上回った。その後も「仕事」の「宣伝」のために、私は広烏の空を飛び回った。この「小田億家具号」には、延べニ千回ぐ らいは乘っただろうか。グライダーの曳航も やった。お客さんも乗せた。あれやこれや、 宣伝効果は予測をはるかに超えた。私自身が 驚いた。というのは、広島の街で初めての人に会った時、「小田億です」と言えば、「あの 飛行機の」と返ってくる。家具センター丨のお 客さんに何年間かアンヶート調査の協力をしてもらったことがある。「小田億家具をどうして知りましたか」の回答九九%が「飛行機 で」だった。
また、昭和四十四、五年ごろ、専門の広告代理店に当時の金百万円で本格的な調査をしてもらったところ「分析の結果、お宅の知名度は福屋百貨店並み」と言われたのには少々驚いた。「道楽」と「仕事」が、これほどうまくかみ合ってくれようとは?。当初の”ひらめき”の中にもここまでの計算はなかった。
この「小田僚家具私の事業と同心一体、ともに働き続けてきてく れた小田億家具号に感謝する。強い愛着がある。白地の胴体に「小田億家具」のあの黒い大きな文字がまぶたに浮かぶ。ほんとうにありがとう。ご苦労さんでした。
長い長いアルゼンチン世界選手権大会道草の旅だった。一月の末に日本を旅立って、やっ と帰国したのは桜も散った四月の中ごろか。
すぐ家具業の準備にかかる。まず、国内の家具店を回ってみた。大きい所で店舗面積がニ、三百坪ぐらい。よし、そんなら倍の五百三十坪を造ってやろう。やるとなつたらどうせやるんだから家族に心配かけまい、自分も迷うまいとだれにも話さずに猪突猛進。
設計にかかる。その年の九月一日、広島市西区横 川町一丁目の現在地に四階建てのビルが建ちだした。ここまでくれば家族も気付く。「ビル建ててどうするの?」と家内が聞く。「家具をやるんじゃ」。いつものことだから、家内も別に驚くふうもない、もちろん褒めてはくれんが「材木」より「家具」の方が気には入ってい る、そんな感触を受けた。
こんな調子でビル建設は進んだ。規模としては当時、中四国地方では一番大きかった。
翌年、つまり昭和三十九年の春、待望の新事業「家具センター小田億」は華やかに開店し た。オープニングが三月七日、「ラツキーセブン!」と気をよくした。神武か岩戸か知らな いが世の中も隨分華やぎ景気づいた年だった。そうそう、東京オリンピックの年だった。家

「小田億家具号」、市街上空を飛び回る(太田川放水路上空)
具センターが開店して間もなく、これまた念願の自家用飛行機が到着した。さあ、忙しくなった。新事業は発足したばかり、飛行機は乗りたいし、体は一つ。そこで一計、いや、”ひらめき” とでも言わせてもらおう。
「新事業の宣伝、つ まり広告代わりに飛ぼう」。なかなかのグッド アイディアである。
翼へは赤地に白く「小田億家具」、白い胴体には黒字で「小田億家具」。文字を目いっぱい 大きく書き入れた。
たまたま、オリンピックの聖火が広島の街を 走った。沿道は大変な人出でにぎわっていた。 私は空から聖火ランナーに寄り添うような低空 で、飛んでは引き返し、引き返しては飛んだ。 反響は予想をはるかに上回った。その後も「仕事」の「宣伝」のために、私は広烏の空を飛び回った。この「小田億家具号」には、延べニ千回ぐ らいは乘っただろうか。グライダーの曳航も やった。お客さんも乗せた。あれやこれや、 宣伝効果は予測をはるかに超えた。私自身が 驚いた。というのは、広島の街で初めての人に会った時、「小田億です」と言えば、「あの 飛行機の」と返ってくる。家具センター丨のお 客さんに何年間かアンヶート調査の協力をしてもらったことがある。「小田億家具をどうして知りましたか」の回答九九%が「飛行機 で」だった。
また、昭和四十四、五年ごろ、専門の広告代理店に当時の金百万円で本格的な調査をしてもらったところ「分析の結果、お宅の知名度は福屋百貨店並み」と言われたのには少々驚いた。「道楽」と「仕事」が、これほどうまくかみ合ってくれようとは?。当初の”ひらめき”の中にもここまでの計算はなかった。
この「小田僚家具私の事業と同心一体、ともに働き続けてきてく れた小田億家具号に感謝する。強い愛着がある。白地の胴体に「小田億家具」のあの黒い大きな文字がまぶたに浮かぶ。ほんとうにありがとう。ご苦労さんでした。
父の駆け抜けた人生の象徴とも言える「小田億家具号」は現在、横川本店の駐車場にモニュメントとして展示してあります。
この飛行機は小田億の象徴でもあり、父の魂そのものと言っても良いものでした。
多くの広島市民に親しまれた小田億家具号、そして小田億はこのように誕生しました。
おかげさまで小田億も創業113周年を迎えることができたのも、多くの方々のご支援ご鞭撻のおかげと感謝しております。
まぶたを閉じれば父が今でも広島上空を飛び回っているような気がします。
この飛行機は小田億の象徴でもあり、父の魂そのものと言っても良いものでした。
多くの広島市民に親しまれた小田億家具号、そして小田億はこのように誕生しました。
おかげさまで小田億も創業113周年を迎えることができたのも、多くの方々のご支援ご鞭撻のおかげと感謝しております。
まぶたを閉じれば父が今でも広島上空を飛び回っているような気がします。
小田基治